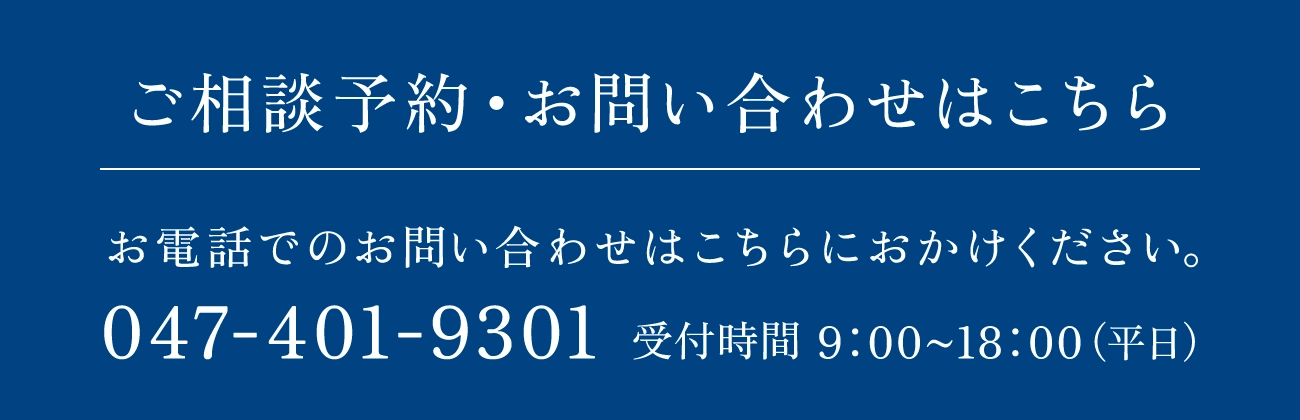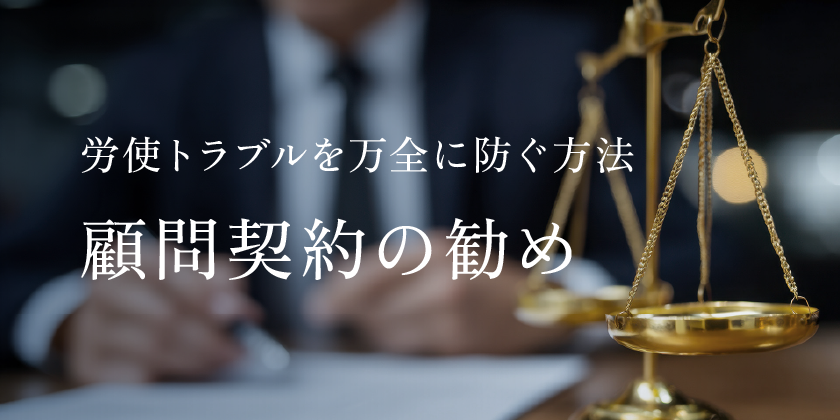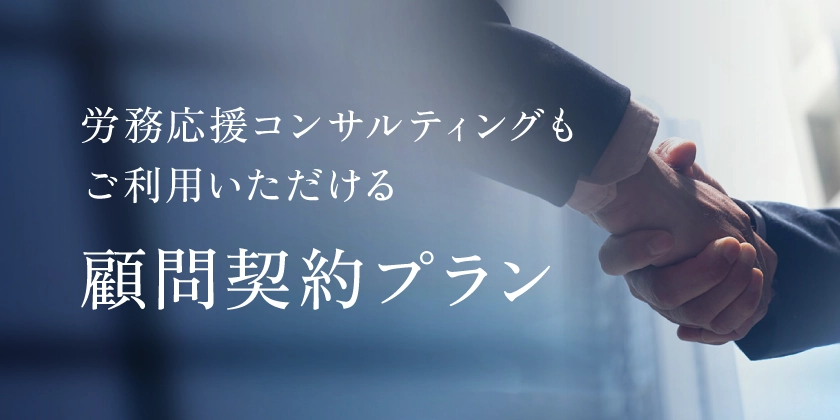賃金制度改革 労務応援コンサルティング
このようなお悩みを持つ企業におすすめします
- 働き方改革に合わせて賃金制度を見直したい。
- 旧来型の年功序列の賃金制度の改革を法的に問題なく進めていきたい。
- 同一労働同一賃金に対応できる賃金制度の設計に向けて人事制度を含めた大改訂を行いたい。
- 未払残業代のリスクのない契約書・賃金規程を作りたい。
- 時間外労働のことで労働基準監督署の調査が入ってしまった。
- 労働者から未払残業代を請求された。
穴のある賃金制度に潜む未払賃金・未払残業代等のリスク
近年、労働者からの未払残業代請求が増加しています。
こうした未払残業代の請求を受けている企業のご相談を受けますと、賃金制度そのものに欠陥があるケースが多く見られます。
また、改正有期・パートタイム労働法では「同一労働同一賃金」の対応が必要とされています。
期間雇用労働者やパートタイム労働者から、正社員との賃金格差を請求される事件も増えています。
同一労働同一賃金が導入された令和時代においては、旧来型の年功序列の賃金制度からの脱却と、賃金制度の大幅な改革が求められています。
仕事内容や責任内容に合わせて「職務」に合わせた等級制度の構築して、仕事をしっかりとこなす従業員が適切に評価される制度を導入する動きが進んでいるのです。付随して、人事制度評価の構築のニーズも高まっています。
賃金制度改革については、税理士の先生の税務上アドバイスや、賃金コンサルタントのアドバイスにより実施している企業も多くあると思います。
しかし、賃金制度を構築するに当たっては労基法・労働契約法等の諸法令との整合性を考慮しつつ、労使紛争のリスクを加味した作成が不可欠です。賃金制度の不備は労働トラブルに最も直結する場面です。
会社と従業員に合った賃金と評価制度を
賃金制度や人事評価制度は会社に合っていることが大前提です。どこかに落ちている制度をそのまま拾ったり、コンサル会社が提供する賃金制度やルールをそのままに使うのは大変危険です。
今は同一労働同一賃金などの法的な問題が無いことは当然として、人財を活かして企業が成長するための賃金制度の導入を検討するという対応が必要なのです。
弁護士に依頼するメリット
適切な賃金待遇を整備すれば職場のアピールポイントとなることから、優れた人材の獲得に繋がり、既存の優秀な従業員の離職防止にも繋がります。
ただ、賃金制度の改革は、一方で賃金が下がる等の不利益が生じることもあり、法的にクリアすべきハードルは少なくありません。
仮に制度変更が無効とされてしまった場合、過去の制度が適用されてしまうこととなり、過去の未払賃金の請求トラブルになるだけではなく、社内でも大きな混乱を招くことになります。
同一労働同一賃金の規定が整備されたことにより、適切な措置を行うことは法律上必須となりました。これに違反した場合には、従業員から損害賠償請求などの訴訟を提起される可能性もあります。
労務応援コンサルティングとは?
労務応援コンサルティングは、弁護士法人戸田労務経営オリジナルの顧問契約サービスです。
弁護士法人戸田労務経営では、顧問契約のC・B・A・S・SSの各プランに応じて、労務の各ステージに応じた顧問サービスを行っています。
他の「労務応援コンサルティング」はこちらをご覧下さい。
賃金制度改革コンサルティング
弁護士法人戸田労務経営では、企業での賃金制度改革に必要な労務・法務を万全にフォローする「賃金制度改革 労務応援コンサルティング」を行っています。
労務専門の弁護士が、現状の賃金制度を詳細にヒアリングさせていただき、賃金制度の不備・労務上の問題点をチェックさせていただきます。最近は人事評価制度の導入事例も増えてきております。
ご要望に添った賃金制度改革を、労働法務を踏まえてコンサルティングさせていただきますので、万全な対応を取ることが可能です。
①賃金制度のトータルチェック
②賃金制度改革サポート
職務等級制度や同一労働同一賃金に合致した賃金制度等の導入のアドバイス
人事制度評価制度の導入サポート
③労働契約書・規程の制定
関係書類全般を②の制度に合わせて全て準備します。
④賃金制度の運用サポート
⑤給与計算手続の代行
解決事例
戸田労務経営では、賃金制度の改革、人事評価制度の導入など、数多くの事例を対応してきました。
以下はその一例をご紹介します。
職務の整理を含めた賃金制度の改革により、同一労働同一賃金への対応も実現した事例
ある会社では、従前は正社員・パートタイマーの2区分しか存在しなかったところ、パートタイマーにはあらゆる手当が支給されない等、同一労働同一賃金の観点からも問題が多かったため、その改革に着手しました。
従業員の多様な働き方に対応しきれていない状況もあったため、まずは社員の区分を、限定正社員の創設など実態に合った柔軟な形に変更しつつ、賃金改訂に取り組みました。
正社員の待遇を全て洗い出しつつ、パートタイマーとこれを比較して、合理性のある区別かどうかの整理からスタート。最終的には実態に合った形で、給与制度全体を改革することができました。
職務を評価する人事評価制度を導入した事例
年功的な給与制度を刷新したいというご要望を受け、人事制度の改訂から取り組みました。
会社の理念等に立ち返りながら、求める人材に合わせたコースと職務等級を整理、さらに人事評価項目についての策定をサポートしました。
この制度設計と賃金の座組を合わせていき、「頑張った人」を適切に評価する人事評価制度を実現しました。
完全歩合給制度の導入をした事例
運送会社において、稼ぎに応じた歩合給制度を導入するサポートを行いました。
自身の売上を上げれば比例して給与が上がっていくことを望むドライバーも多い会社ですし、歩合給制度は残業代計算の仕方が通常の固定給と比べて特殊でして、未払残業代の抑制効果も期待できます。
ただし、歩合給制度が否定された裁判例もあるため、弁護士の目を入れて適切に制度設計をすることが重要です。
法的に問題のない歩合給制度の構築、リスクヘッジのための制度導入、従業員への説明資料などを含めて対応し、完全歩合給制度の導入を実現した事例です。