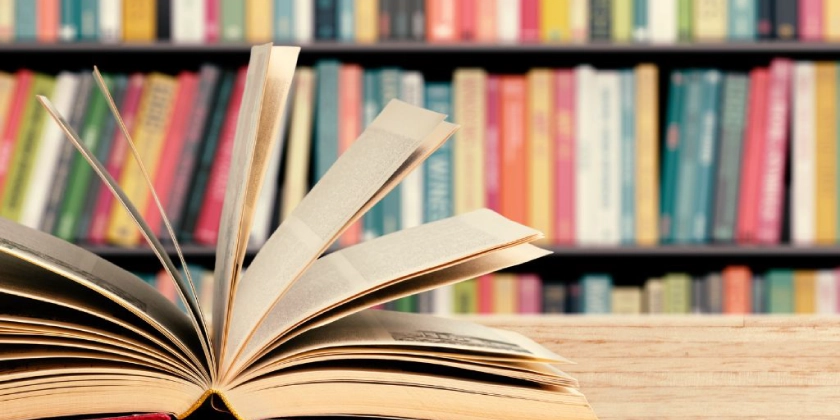労働問題でお悩みの企業の方へ
使用者側の皆様にとって、人を使って企業活動を行う以上、労働問題は日常的に発生する可能性のある、非常に身近な問題です。
優秀な「人材」を確保して、円滑な企業活動を行うためには、労働問題のトラブルの起きない組織を作っていくことが極めて重要です。
弁護士法人戸田労務経営では労働問題をあらゆる立場から総合的に解決することを目指しています。
代表弁護士の戸田は、かつては労働者側事件も多数解決してきた経験があります。
使用者側としての労働交渉、労働審判、労働訴訟、労働組合対応、顧問対応等の経験も豊富であり、数々の勝訴的解決や紛争防止を実現してきました。
弁護士法人戸田労務経営では、こうした多種多様で、労使双方の労働事件の解決経験があります。
労働者側の立場での主張も熟知しているからこそ、使用者側に立った場合に、労働者の一手二手先を読み、さらにはその心理状態を踏まえた交渉・協議を行うことが可能なのです。
労使双方の立場から労働問題を総合的に解決し、少しでも労働紛争のない社会を作る。
これこそが、弁護士法人戸田労務経営のモットーであり、使用者側しか扱わない弁護士にはない強みであると自負しております。
使用者の皆様のために全力を尽くして闘うことをお約束致します。
対応する弁護士は、弁護士法人戸田労務経営所属の弁護士です。
全国の労働問題に「いつでも、困ったときに」対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
以下では、労務テーマごとに弁護法人戸田労務経営ができること等をまとめています。
労働問題に悩む企業の皆様の参考になれば幸いです。

顧問の社会保険労務士の先生が付いている企業も多いと思いますが、労務問題については弁護士にしか解決できないことがあります。弁護士へ相談するメリットや意味について解説します。

従業員を採用した後に試用期間を設けている企業は多いと思います。また、試用期間が終了する際に、今ひとつ出来が期待外れな場合、本採用をするかどうか決めかねる場合もあります。試用期間の決め方のルール、試用期間の対応方法等について解説します。

正社員について試用期間の満了をもって本採用拒否をするとした場合、試用期間満了のタイミングで退職をさせることは可能なのでしょうか。その際の労務トラブルも含めて解説します。

人事異動として配置転換、出向、転籍等に関する法律上のルールについて解説します。例えば東京本社から仙台支店への配属変更(いわゆる配転)ができるかどうか、職種や勤務地の限定についても解説します。

賃金に関する労働法のルール全般を解説します。例えば、レジ打ちをミスして金額が合わないと、1回につき「罰金1000円」を給料から引くことは労働基準法に違反すると言われます。未払賃金による企業のリスクも解説します。

就業規則の役割、労使トラブルを防ぐ就業規則について解説します。インターネットで推奨されていた就業規則を会社の実情に合わせずにそのまま使うことのリスクについても解説します。

労働条件の不利益変更については、労働契約法や判例などでルールが決まっています。基本給の減額、手当の廃止、定期昇給の廃止、年間の所定休日の削減等が典型ですが、どのようなルールがあるか等解説します。

従業員の労働条件を変更する具体的な方法について解説します。労働条件の変更は、①労働者の同意、②就業規則の変更、③労働協約の変更によって行う方法がありますので、それぞれについて解説します。

未払い残業代とは、従業員に対して法律で定められた時間外労働や休日労働、深夜労働に対する賃金を支払っていない状態のことを指します。こうした未払残業を発生させた場合の企業のリスクなどについて解説します。

退職勧奨とはどういう位置づけか、退職勧奨が無効になったり、慰謝料請求をされてしまうようなことになるのはどういう場合かなど、退職勧奨のトラブルについて解説します。

従業員が労災事故で死亡したケース、特に過労死や過労による自死などについての解説をしています。労災認定の基準や安全配慮義務違反による賠償責任についても解説します。

問題行動の多い従業員について、解雇したところ、「会社の理由には全く納得できない、不当解雇だ!」と訴えてくるケースがとても増えています。仮に不当解雇だった場合の会社のリスクとはどんなものか解説します。

会社がやるべきパワーハラスメント(パワハラ)の防止と対応方法
昨今パワーハラスメントの問題は労務相談のトップの一つです。指導との線引きが非常に難しいこともありますが、ここではパワハラの定義や防止体制づくり、パワハラ加害者への対応について解説します。

企業は労災事故が発生した場合にどのように対応すればよいでしょうか。労災の企業の対応、労災が発生した場合の企業のリスクを解説します。企業が履行すべき安全配慮義務についてもここで解説します。

どんな場合が労働災害(労災)になるか。労働災害(労災)になった場合、労災保険ではどのような給付がされるか。また、労災保険とは別に会社が民事賠償の請求を受ける場面等について解説をしています。

メンタルヘルス不調の疑いがある従業員の対応については、かなり悩ましいものがあります。ここでは、メンタルヘルス不調発見の方法や私傷病休職の発令など、企業がメンタルヘルス問題にどう取り組むべきかについて解説します。

病気や精神疾患で会社を休む従業員について(休職に関するトラブル)
メンタルヘルス不調等の私傷病で長期の欠勤をする従業員への対応が課題となっている企業は多いです。ここでは、私傷病休職の制度について詳細な解説をしています。

同業他社への転職・独立を考えている方へ(競業避止義務について)
独立して企業の立ち上げを決意した際、前職との競業関係が問題となることがあります。競業避止義務というものですが、これはどういった義務なのでしょうか。競業避止義務が有効となるための判断基準などについても解説しています。

非正規労働者(アルバイト・パート・契約社員)の労務管理上の注意点
学生を含めたパートやアルバイトの社員が多い企業では、非正規雇用の従業員の労務管理が課題になります。同一労働同一賃金のルール、有期雇用契約についての雇止めルールや無期転換等の詳細を解説します。

企業においては、部下を統括する管理職として責任のある人材の活用が欠かせません。こうした管理職は、労基法の管理監督者として労働時間の規律を受けない扱いとされていることが多いです。管理監督者の判断要素等を含めて解説します。

労働事件の紛争解決には、裁判以外の方法も含めて様々な解決方法があります。各手続の内容や特性を理解することで、実際に紛争化した場合にも適切な判断ができます。ここでは労働事件の解決手続の全体像を解説します。

昨今、労働者が外部のユニオンに加入し、団体交渉を申し入れてくるケースが増えています。団体交渉の対応の基本、団体交渉を拒否できるケースがあるか等について解説をします。

従業員に訴えられた場合(内容証明が届いた、あっせんを申し立てられた)
従業員本人や労働者の代理人である弁護士から、内容証明を送られる等の請求をされる場面は、紛争の初期段階です。訴訟外の交渉として、適切に初期対応を行うことがとても重要です。ここでは労使交渉の進め方について解説しています。

労働審判という手続は、最近の労使紛争解決手段として非常によく取られるものです。相手に弁護士が付いていれば特にこの申立をされることが多いです。この手続は、弁護士の経験値等も含めて対応に非常に差が出るものです。労働審判の基本的な対応について解説します。
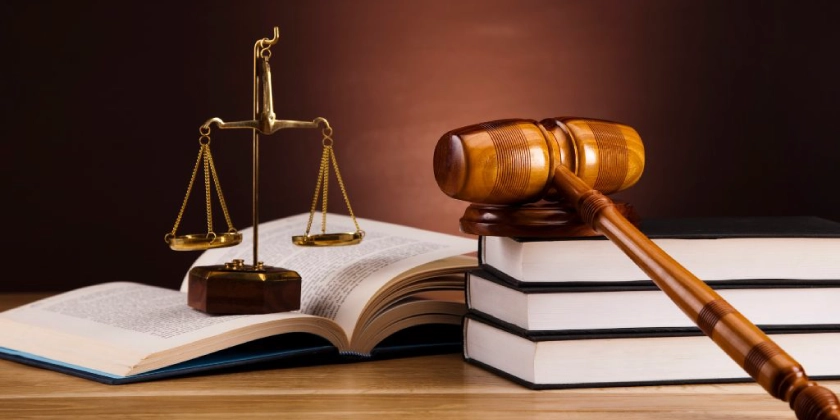
裁判所から訴状が届く、仮処分申立書が届く、という段階は労使紛争がかなり激化した状態です。それぞれの手続の内容を含めて、企業がどのように対応すべきかを解説しています。