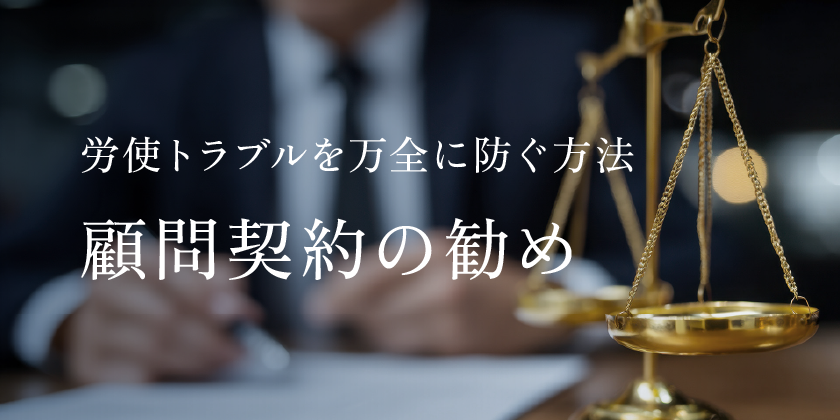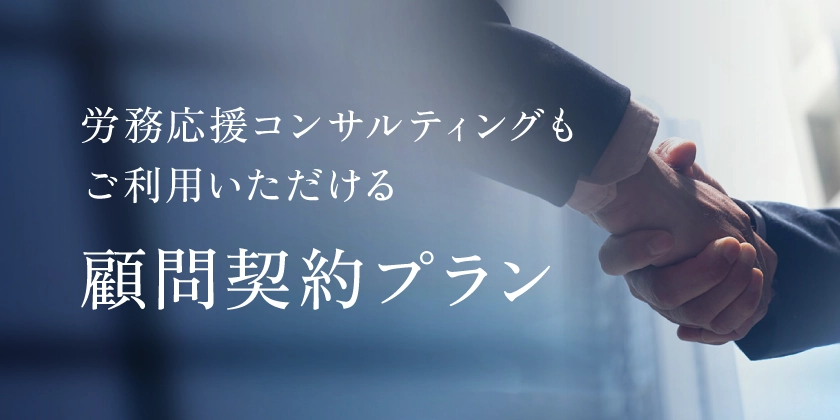従業員が労災事故(過労死)で死亡した場合の企業対応
相談内容
弊所は広告会社です。弊所のプロジェクトマネージャーの従業員が、大きなプロジェクトが終わった後に自死してしまいました。
確かに、このプロジェクトをこなすため、かなりの残業はしていらっしゃいましたし、ストレスもかなりかかっていたのだと思います。
実際、遺書には、長時間の仕事のストレスや、上司からのパワハラがあったこと等が書かれていたようです。うつ病の診断も受けていたようです。
ご家族へ謝罪に伺ったのですが、「会社に殺されたも同然だ」と言われてしまい、門前払いにされてしまいました。
当然のこととは思いますが、この先会社はどのように対応をすべきでしょうか。また、こうした場合労災の認定がされるのか、会社が賠償の責任を負うのかこのあたりも教えて下さい。
回答
大切な従業員の方がお亡くなりになったとのこと、お悔やみ申し上げます。
まずはご遺族に対して誠意を持った対応をすることは大前提になります。
労災について、こうした精神疾患による自死の場合にまず考えられるのは、業務起因性が認められるかどうかに関わってきます。長時間労働が一定の過労死基準以上であったり、パワハラという事実が本当であったりすれば、労災認定の可能性が高いです。
また、長時間労働を強いている事実等から会社の安全配慮義務違反が認められれば、労災保険では填補されない損害についても賠償請求を受けます。
賠償の内容としては、死亡に対する慰謝料や将来の逸失利益等が含まれますので、多額の請求になるケースが多いでしょう。
解説
過労死・過労自殺の場合の労働災害(労災)の認定
近時、有名企業の過労自殺が報道されたように、長時間労働等に起因して労働者が精神障害を患って、自殺してしまうという過労死・過労自殺の事案は未だ後を絶ちません。
まず考えられる方法は労働災害(労災)給付です。
労働災害(労災)の詳しい内容については、こちら「労災事故の取り扱いについて」
労働者の死亡の際の労災給付
労働災害(労災)によって労働者が死亡した場合は、遺族補償年金等の遺族補償給付の支給がされます。
遺族補償年金は、受給権者及びその者と生計が同じ人の人数に応じて支給されます。
過労死の労働災害(労災)認定基準
長時間労働等の仕事による疲労やストレスが蓄積して、脳・心臓疾患(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞等)を発症して死亡するに至ったものが、いわゆる過労死と言われています。
こうした脳・心臓疾患等による過労死については、厚生労働省が「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」という認定基準を出しています(平成13年12月12日基発1063号)。実務上この基準が前提とされています。
この認定基準では、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等が自然経過を超えて著しく憎悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があるとし、そのような経過をたどって発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断される、との考え方をとっています。
【業務による明らかな加重負荷とされる場面】
- 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的および場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
- 発症に近接した時期(概ね1週間)において特に過重な業務に従事したこと
- 発症前の長期間(概ね6ヶ月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
※「過重な業務」かどうかについては、量的な過重性と質的な過重性が問題です。
量的な過重性については、発症前1ヶ月間に概ね100時間、発症前2ヶ月間~6ヶ月間にわったって1ヶ月当たり概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合は業務との関連性が強いと判断されています。
質的な過重性については、勤務の不規則性、劣悪・過酷な作業環境、精神的緊張を伴う業務であるかどうか等が問題になります。
上記のとおり、労働時間が長時間にわたる場合、睡眠不足などの長期化によっての影響が大きいと考えられることが多くなります。
上記の時間外労働の水準がいわゆる「過労死基準」と言われるものでして、こうした過労死基準を超えての過重労働を課していた場合には労災認定されるリスクが一気に高まります。
精神疾患による労働災害(労災) 認定基準
労働者が、業務上の疾病として発病した精神障害のために自殺した場合は、別途精神疾患の発症についての労災認定が問題になります。
こうした場合の労災認定については、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日基発1226号第1号)が基準を定めており、実務上の指針として重要です。
- 対象疾病の発病していること(発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があること)
- 当該対象疾病の発病前の概ね6ヶ月の間に業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷及び個体側要員により対象疾病を発病したとは認められないこと
ここにおいても上記と同様に時間外労働過労死基準が重視されます。
民事賠償責任(安全配慮義務違反)の追及
労災保険では支給されない損害の請求
以上の労災給付が認められたとしても、死亡慰謝料や死亡逸失利益等は支給されませんが、会社が民事賠償責任を負う場合には問題となります。
死亡慰謝料については、通常数千万単位の賠償になります。
また、死亡逸失利益は、亡くなった労働者の方が生涯働いて得られるはずであった賃金相当額を請求することになりますから、数千万以上になることも珍しくありません。
会社の安全配慮義務違反を追及する
会社に「過失」(安全配慮義務違反)があれば、こうした損害賠償責任が生じます。
実際の裁判においては、その過失については、労働者側で組み立てて、証拠によって証明することが求められることとなるのですが、精神疾患や脳・心臓疾患による労災認定がされた場合には、基本的に安全配慮義務違反が認めらえることが多いのが実際です。
弁護士への相談
労災によって従業員が死亡してしまうケースは一大事です。当然遺族の方が弁護士を付けて交渉を求めてくることを想定して対応をしなければなりません。
誠意をもってしっかりと対応することは重要ではありますが、やはり法的な部分を含めて早期に、経験のある弁護士への相談をすることは不可欠かと思います。