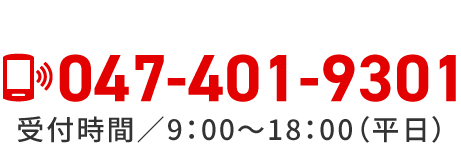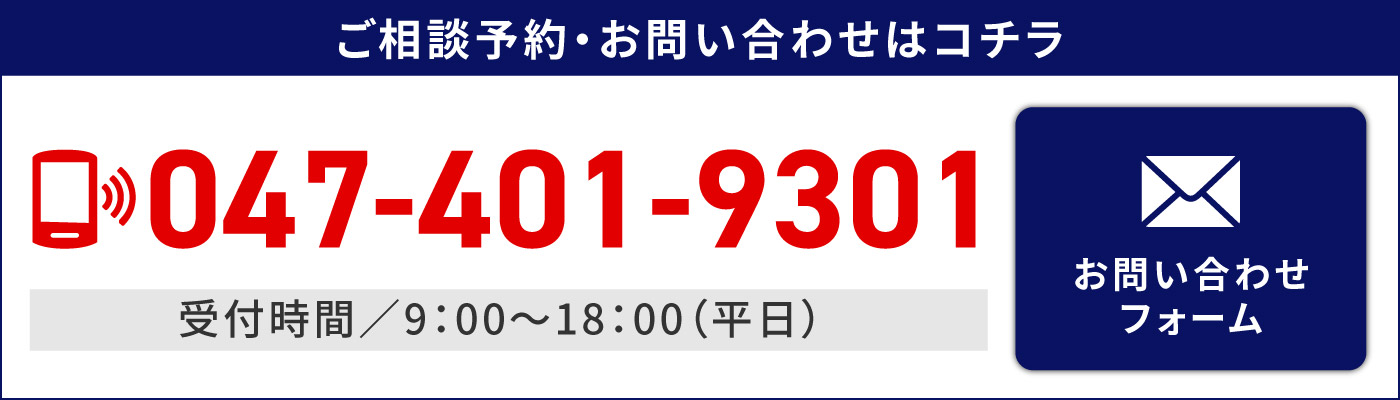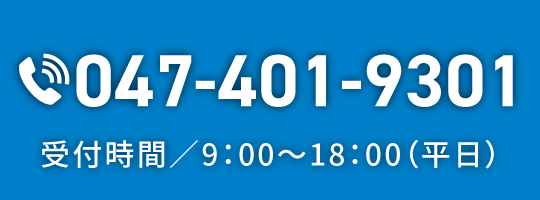はじめに~事業場外労働みなし制度とは~
令和6年4月16日に、事業場外みなし労働時間制に関する最高裁判決(協同組合グローブ事件)が出ました。
事業場外みなし労働時間制というのは、労働者が労働時間の全部又は一部について、事業場施設の外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときに、その日は所定労働時間だけ労働したとみなす制度です(労働基準法38条の2)。
たとえば、所定労働時間8時間の労働者が、実際には事業場の外で所定労働時間を超えて10時間労働をした日があったとしても、この制度の適用があれば所定労働時間の8時間を労働したものとみなされるということです。つまりは時間外労働の残業代を削減する手法としても機能するということです。
これは裁量労働制度等とは全く別の、みなし労働時間制度です。
この制度は本来、取材記者、外勤営業社員など、常態的に事業場外労働をする労働者や、出張等で臨時に事業場外労働をする場合等を想定し(改正前の労基則22条)、労働時間の算定の便宜を図るためのものでした。
最近では、テレワークの場面も事業場外労働みなし制度が運用されることが想定されています(厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン」2021年3月)。
ただ、この制度は従前から非常に適用例が絞られていた実情があります。
その理由は、「労働時間を算定しがたいとき」という労働基準法の要件のハードルがとても高いとされているからです。
※外勤・在宅勤務者等への事業場外労働みなし制度の導入に関するサポートはこちら
「労働時間を算定し難いとき」の要件のハードル~阪急トラベル・サポート事件最高裁判決
「労働時間を算定し難いとき」とは、事業場外で行われる労働について、
その労働態様ゆえに[労働時間を十分に把握できるほどには使用者の具体的指揮監督を及ぼし得ない場合]
とされています(引用:菅野和夫「労働法(第13版)」472頁)。
一見、労働者に時間の裁量を与えており、タイムカード等の管理をしていない状況ならこの要件を満たすようにも思えますが、そう簡単ではありません。
そもそも使用者には労働者の労働時間を把握する義務が課されていますので、単に「把握しなかった」のであれば、単なる義務違反です。
ここについてリーディングケース(先例)とされているのは、最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決(阪急トラベル・サポート事件)です。
この判決は、旅行会社が企画・催行する国内・海外のツアーのために派遣会社から派遣されたツアー添乗員の事業場外労働みなし制度の適用が問題となりました。
ここで出てくるツアー添乗員は、担当ツアーの割り当てを受けて、ツアー参加者と空港で待合せて飛行機に同乗し、ツアーの計画に沿って旅行先を同行して帰国するというという流れで業務をします。
国内・海外いずれも事業場外で労働を行っていくわけですから、会社側でなかなか「労働時間を算定」することは困難なケースのようにも思えました。
ところが、この最高裁判決は、以下を理由として「労働時間を算定し難いとき」には該当せず、制度の適用を否定したのです。
- ツアーの旅行日程について日時・目的地等が事前に確定されている
- ツアーの出発から帰着までの詳細な行程とその管理の仕方が指示され、それらをできるだけ遵守しなければならない
- 実際の行程についても添乗報告書に詳細に記載させてこれを会社に提出しなければならない(報告の内容については、ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができる)
- 会社が、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅程の変更が必要となる場合には、本件を会社に報告して指示を受けることを求めている。
添乗報告書のような報告書が労働時間の把握の手がかりとされていますが、こうした報告書の類がなければ、実際に勤務を行ったかの確認もできませんので、事業場外勤務においては普通提出されるものです。
また、いまどき携帯電話やスマートフォンを所持しないで外勤をするケース等は稀というべきです。
このような最高裁判決が出たことで、通常の外勤勤務の労働者に事業場外労働みなし制度を適用することは相当ハードルが高い、という印象を持っていました。
さて、それだけに今回の最高裁判決である協同組合グローブ事件の判断は注目でした。
この事件は、上記の阪急トラベル・サポート事件最高裁判決のような判断からすると、今回も事業場外労働みなし制度の適用は厳しいのではないかと思われる事案でした。
実際、原審(熊本地裁と福岡高裁)では事業場外みなし労働制度の適用が否定されたのですが、最高裁判決はこの原審判断を破棄したのです。
※外勤・在宅勤務者等への事業場外労働みなし制度の導入に関するサポートはこちら
協同組合グローブ事件の事案の概要
これより、協同組合グローブ事件の事案を説明致します。
なお、この事件の熊本地裁判決(令和4年5月17日)の際には、事業場外みなし労働の争点はあまり注目されていませんでした。
地裁判決で注目されたのは、労働者である原告(Ⅹ)が訴訟提起の際に行った記者会見が被告(Y、協同組合グローブ)の名誉・信用を毀損したとして損害賠償の支払が認められた点でした。
労働者側の記者会見が名誉棄損になるケースというのはあまり例がなかったためです。
さて、最高裁での争点は事業場外労働みなし制度の有効性に絞られています。
事案ですが、労働者である被上告人(ここから「Ⅹ」と言います。)が、事業場外労働みなし制度が無効であると主張して、勤務先の上告人(Y組合)に対して、実働時間に沿った未払残業代を請求したという内容です。
概要は以下のとおりです(最高裁の認定に登場しない地裁判決の認定内容も含んでいます)。
| 被上告人(Ⅹ) | 平成28年9月、外国人の技能実習に係る監理団体であるY組合に雇用され、指導員(キャリア職員)として勤務したが、同30年10月31日、上告人を退職した。 |
| 業務内容 | 自らが担当する九州地方各地の実習実施者に対し月2回以上の訪問指導を行うほか、技能実習生のために、来日時等の送迎、日常の生活指導や急なトラブルの際の通訳を行うなどの業務に従事していた。 【参考(雇用契約の「従事すべき業務の内容」)】 外国人技能実習生及び建設/造船就労者への相談対応、訪問・巡回指導、監査、通訳、講習、付帯業務 |
| 業務内容の管理・報告体制 | 本件業務に関し、実習実施者等への訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理していた。 また、Ⅹは、Y組合から携帯電話を貸与されていたが、これを用いるなどして随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることはなかった。 |
| 就業時間と実際の労働時間 | 午前9時から午後6時まで、休憩時間は正午から午後1時までと定められていたが、Ⅹが実際に休憩していた時間は就業日ごとに区々であった |
| 労働時間の管理 | Ⅹはタイムカードを用いた労働時間の管理を受けておらず、自らの判断により直行直帰することもできたが、月末には、就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報をY組合に提出し、その確認を受けていた。 |
原審(高裁判決)判決の概要~業務日報を重視してみなし制度を否定
事業場外みなし労働についての原審の判断は次の通りです。
| 【高裁判決の判断】 Ⅹの業務の性質、内容等からみると、Y組合がⅩの労働時間を把握することは容易でなかったものの、Y組合は、Ⅹが作成する業務日報を通じ、業務の遂行の状況等につき報告を受けており、その記載内容については、必要であればY組合から実習実施者等に確認することもできたため、ある程度の正確性が担保されていたといえる。 現にY組合自身、業務日報に基づきⅩの時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったものであり、業務日報の正確性を前提としていたものといえる。以上を総合すると、本件業務については、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。 |
熊本地裁も福岡高裁のいずれも、本件は「労働時間を算定し難いとき」には該当しないと判断しました。
ここで重視されたのは業務日報です。
先にお話した阪急トラベル・サポート最高裁判決も、添乗日報が重視されていましたが、これと同様の考え方を取ったのです。
最高裁の判決文では詳細は記載されていないのですが、業務日報は「キャリア業務日報」というものでした。
訪問先への直行の有無、始業時間、終業時間、休憩時間のほか、行先、面談者及び内容とともにそれぞれの業務時間を報告する内容であることが、熊本地裁判決では認定されています。
さらに、この業務日報は毎月月末までに所属長に提出されて、支所長が明らかな誤りがないかを審査して確認印を押していたという実態についても熊本地裁では認定されています。
このような業務日報による報告を受けていれば、Y組合もその記載内容を確認したり面談者に確認することで、労働時間の把握はできる、という判断でしょう。
Y組合も残業代計算の根拠として使っていたものであるから、業務日報の正確性はある程度担保できているということもその根拠の一つとなっています。
最高裁判決の判断①~業務の性質と具体的指示がなかったことを重視
さて、いよいよ協同組合グローブ事件最高裁判決の判断内容です。次のように判断して原審の判断を覆しました。
| 前記事実関係等によれば、本件業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等、多岐にわたるものであった。 【☜業務の性質、内容やその遂行の態様(注:執筆者加筆)】 また、Xは、本件業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものといえ、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったものである 【☜業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況(注:執筆者加筆)】。 このような事情の下で、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば(注:執筆者下線)、Xが担当する実習実施者や1か月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、Y協同組合において、Xの事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い。 |
阪急トラベル・サポート事件最高裁判決では、「労働時間を算定し難いとき」に該当するかどうかについて、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮するとした内容に沿った検討をしています。
この判断基準は変わらず踏襲されていて、既に確立された感があります。
補足意見も、以下のとおり指摘します。
「これらの考慮要素は、本件規定についてのリーディング・ケースともいえる最高裁平成24年(受)第1475号同26年1月24日第二小法廷判決・裁判集民事246号1頁が列挙した考慮要素とおおむね共通しており、今後の同種事案の判断に際しても参考となると考えられる。」
最高裁は、このリーディングケースの判断基準を前提にしつつも、各要素の実態を見ているという印象です。ここは非常に重要なポイントです。
阪急トラベル・サポート最高裁判決では、同判決の添乗員はツアー行程が決まって、予め確定された枠内で業務をする(自分の判断でツアーの時間を変更することはできず、その場合は会社の指示を仰ぐ)というものでした。しかし、今回の事案とは決定的な違いがあるということです。
今回の事案では、指導員が行うべき本件業務内容は生活指導から何から非常に多種多様です。
相手も技能実習を前提に来日したばかりの外国人ですし、都度対応すべきことは流動的で、予定通りに終わらないことも多々あったことが推察されます。こうした業務内容の性質からすると指導員に内容や時間につき、相当の裁量を与えなければ成り立ちません。
どのように業務を行うかの自主的判断の幅が大きい訳で、携帯電話を持っていたとしてもそれを使って都度指示を受けるという訳ではない、というところに違いがあります。
それゆえ、時間変更等によって逐一業務指示を受けたりすることも無いということでしょう。
業務の性質や内容を出発点にするという、本来の基準の判断要素に立ち戻って検討をしたことの意味は大きいです。
最高裁判決の判断②~業務日報の正確性を再検討せよ
その上で、最高裁は、業務日報を重視し過ぎた原審の判断を否定します。
| しかるところ、原審は、XがY組合に提出していた業務日報に関し、 ①その記載内容につき実習実施者等への確認が可能であること、 ②Y組合自身が業務日報の正確性を前提に時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったことを指摘した上で、その正確性が担保されていたなどと評価し、もって本件業務につき本件規定の適用を否定したものである。 しかしながら、上記①については、単に業務の相手方に対して問い合わせるなどの方法を採り得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明らかでない。 上記②についても、Y組合は、本件規定を適用せず残業手当を支払ったのは、業務日報の記載のみによらずにXの労働時間を把握し得た場合に限られる旨主張しており、この主張の当否を検討しなければY組合が業務日報の正確性を前提としていたともいえない上、Y組合が一定の場合に残業手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正確性が客観的に担保されていたなどと評価することができるものでもない。 |
このように、業務日報を重視して労働時間が把握できるとの結論付けた原審を一蹴します。
①の点は、阪急トラベル・サポート最高裁判決が判断した日報の位置づけをそのまま指摘しているのですが、これは日報の正確性・信用性が大前提だろうということです。
前述のとおり、キャリア職員が相当流動的に自主性をもって勤務をしている以上は、この日報が相当客観的なものでない限りは労働時間把握できるには足りないということですね。
| 以上によれば、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈適用を誤った違法があるというべきである。 |
このように判断して、最高裁は原審を破棄差戻としました。最高裁の考え方を受けつつ、再度高裁で審理されることとなったわけです。
まとめ①~多様な働き方に即して業務の実態を分析・検討すべき
正直に言ってこの判断には驚きました。
上記でお話しした通り、この事件のキャリア業務日報というのはそれなりに詳細な内容が記載されていたようですから、阪急トラベル・サポート最高裁判決と同様の考え方を取った原審の考え方は、ある意味想定内の考え方だったからです。
ですが、業務内容に着目していくと、阪急トラベル・サポート事件と本件では前述したように大きな違いがありました。業務日報等のツール一本でのみでは「労働時間が算定し難い」かどうかは決められません。
ここには、裁判官・林道晴氏の補足意見が刺さります。
| いわゆる事業場外労働については、外勤や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレワークの局面も含め、その在り方が多様化していることがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認められるか否かについて定型的に判断することは、一層難しくなってきているように思われる。 こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があるものと考える。 |
阪急トラベル・サポート最高裁判決の個別判断に引っ張られすぎた感のある原審(私もそうです)への注意喚起のようにも映りますね。
阪急トラベル・サポート事件最高裁判決の事業場外労働みなし制度を判断した判決は、いずれも労働時間が何らかのツールで把握できれば(というよりも、「把握できる可能性があれば」)、「労働時間を把握し難いとき」の要件には該当しないという結論になってしまうかのような印象があったからです。現代ではスマホもパソコンもある時代なので、常に連絡を取り合える状況であれば労働時間を把握できるでしょ、と言われてしまうだろうという感覚でした。
ところが、この最高裁判決は、そうしたツールがあることだけで事業場外みなし労働みなし制度が否定されるわけではない、という考え方で、今一度、基準に立ち戻って判断しましょうということです。
注目すべきは、その業務実態の分析かと思います。阪急トラベル・サポート事件と本判決との分かれ道もその点にあります。
事業場外労働で、時間の幅が読めない仕事に従事して、相当の裁量の幅が与えられ、具体的指示を受けていないのであれば、仮に携帯電話やPCを持っていても、みなし制度の適用はありだということです。
実は、阪急トラベル・サポート最高裁判決の前後の裁判例でも、「労働時間を算定し難いとき」に該当するとの判断をしたものもありました。
たとえば、製薬会社で営業に当たる医業情報担当者(MR)につき、訪問先や訪問スケジュールがその裁量に委ねられ、業務内容の事後報告も軽易であること等の事情の下でみなし制度の適用を認めたセルトリオン・ヘルスケア・ジャパン事件(東京高判令和4年11月16日・労判1288号81号)や、出張や直行直帰の部分についてみなし労働時間制度の適用を認めたヒロセ電機[残業代請求]事件(東京地裁平成25年5月22日労判1095号63頁)等です。
裁量のある営業職や出張の直行直帰の場面等ではみなし制度適用の余地は十分にあるということでしょうね。
ただ、だからといって、安易に時間外労働の削減策として考えすぎるのは禁物です。
実際の労働時間とみなし労働時間数がある程度近づくことが制度適用の前提条件にもなっていると思われるからです。
「この制度では、みなし労働時間数をできるだけ実際の労働時間数に近づけるようにみなし方が定められており、事業場の労使協定によるみなしを行う場合にも、みなし労働時間数は実際の労働時間数に近づけて協定することが要請される。」(菅野和夫「労働法」第13版・472頁以下)
※外勤・在宅勤務者等への事業場外労働みなし制度の導入に関するサポートはこちら
まとめ②~労働時間を把握するツールについても精査すべき
また、事業場外みなし労働時間制を導入するのであれば、労働時間の把握ツールの検討も重要です。
実は、協同組合グローブ事件では、業務日報の他にも労働時間を把握し得るいくつかのツールがありました。ただ、熊本地裁判決は、次のように日報以外は労働時間が把握できるものではないと排斥をしています。
- 月間予定を記載したホワイトボード →具体的な時間が記入されていない
- 時間も記載された週間予定表 →短期間の取組にとどまっている上に業務日報との食い違いも多い
- 訪問予定を入力するスケジュールアプリ →入力されたスケジュールどおりの行動は求められていない
- 訪問・巡回先の入退室の際に「イン」「アウト」とメッセージを送信していたLINE →一時的な取り組みにとどまる
これらのツールも使い方によっては労働時間把握の可能性はあると思いますが、いずれも中途半端なものだったようですね。
前述の裁判例(セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン事件)については、ある時期から会社が貸与しているスマートフォン位置情報をONにした状態で出勤時刻及び退勤時刻を打刻するように指示し、月1回「承認」ボタンを押させる等の対応を取った時点からは「労働時間を算定し難いとき」には該当しないとされています。
このように、スマートフォン等の機器一つ取っても、それを持っているから労働時間が把握できるという短絡的な考えではなく、実際にどんな指示系統がとられていたか、どのように報告をさせていたか等が影響していることが見て取れます。
以上です。今後、働き方が多様化する中で、事業場外労働みなし制度を活用しなければならないケースは出てくると思いますので、今回の判決は非常に参考になりました。