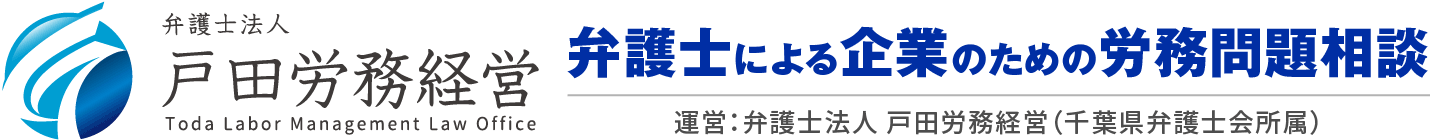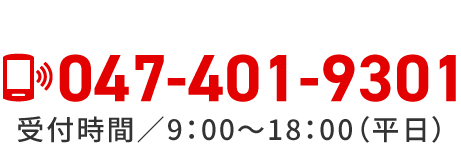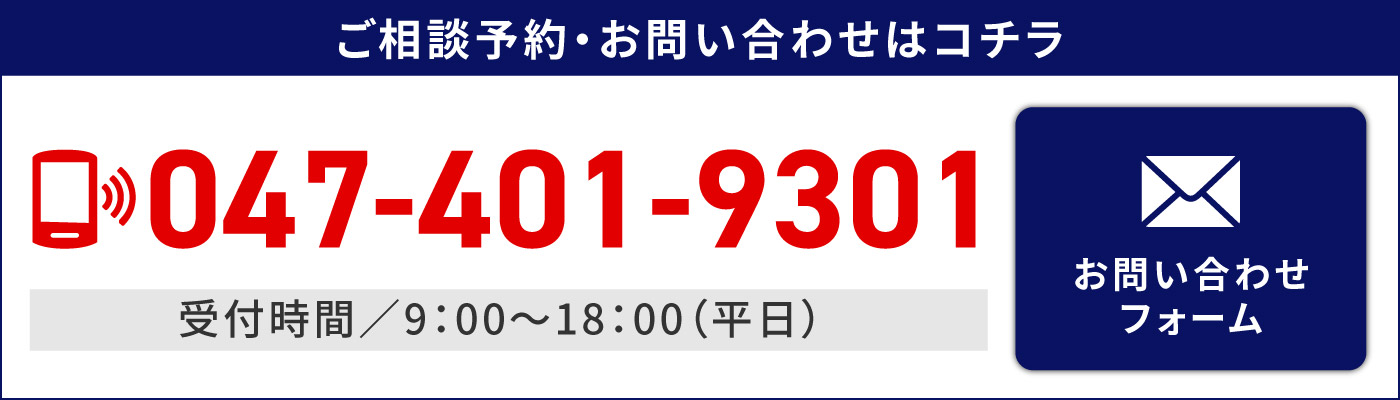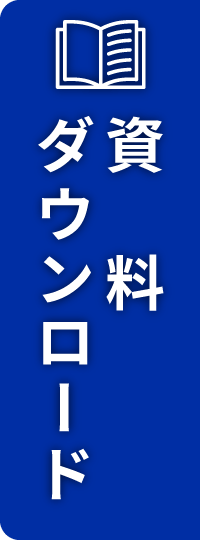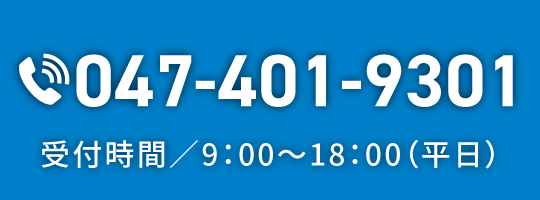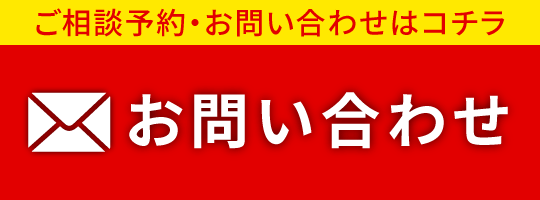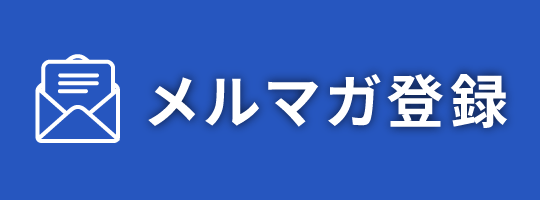相談内容
派遣会社を経営する企業です。
弊社で雇用している派遣社員については、非正規雇用と言われているように、派遣先が「いらない」と言えばいつでも雇用契約を解消することができるのでしょうか。
また、派遣については色々と法律が変わっているようです。派遣社員が派遣先の正社員になる場合があるなど、派遣法は複雑でよくわかりません。
このあたりのアドバイスをいただけると助かります。
回答
派遣先企業の意向等はありますが、派遣社員だからといっていつでも自由に解雇できるわけではありません。
また、一定の場合には、派遣先企業に対して直接の労働契約の成立が認められることがありますので、そうした点を踏まえての労務管理が必須です。
解説
1 派遣社員の立場とは
労働者派遣とは、派遣会社が雇用する労働者(派遣労働者)を、派遣先企業の事業所に派遣して、派遣先企業の指揮命令の下に就業させる形態です。
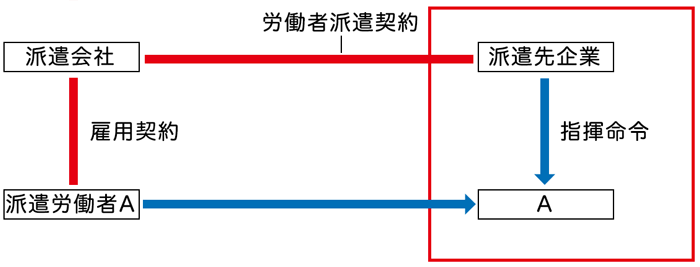
このように、派遣労働者(派遣社員)のAさんは、実際は派遣先企業に入って労働しているのですが、派遣先企業との雇用契約はありません。
雇用契約は派遣会社との間で結んでいるので、派遣会社が使用者となります。
2 派遣社員の保護について
特にリーマンショック以後、派遣社員が次々と契約終了となり、いわゆる「派遣切り」という言葉をよく耳にしました。
現在は、派遣社員の不安定な地位を保護するための規定も定められています。
⑴ 労働者派遣契約が中途解約された場合
よくなされた「派遣切り」は、派遣先企業が労働者派遣契約を打ち切った結果、派遣労働者が失業するという形で表れました。
場合によっては、それを理由として派遣会社が安易に派遣労働者を解雇してしまうこともありました。
労働者派遣契約が契約期間途中で派遣先企業から解約された場合、派遣社員の保護は一切ないのでしょうか。
- 派遣会社から別の派遣先を確保してもらう
まず、派遣契約が残っている以上、派遣会社としては、別の派遣先での就業機会の確保を図る必要があります(平成11労告137号「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」) - 派遣会社との雇用契約の継続に基づいて賃金や休業手当を請求する
ただし、別の派遣先が存在しないこともあります。
その場合に考えられる方法は、派遣元である派遣会社に対して、残りの派遣期間(労働契約の期間)について、賃金全額の支払いを請求する方法や休業手当の支払いを請求する方法です。
もっとも、賃金全額請求を行うためには、派遣会社に帰責事由が認められることが必要ですので(民法536条2項)、少しハードルがあります。
これに対して、休業手当の請求は平均賃金の6割のみの請求です。
労働者派遣契約が打ち切られ、派遣社員が働くことができないことが「労働者の責めに帰することのできない」場合に請求できます。
賃金全額請求の場面よりは認められやすいでしょう。 - 無期雇用の派遣労働者についての解雇禁止
2015年の派遣法改正を受け、派遣会社は、派遣先企業との派遣契約が終了したとしても、それだけを理由として無期雇用の派遣労働者について解雇してはならないとの指針が規定されました(派遣元指針第2の2⑷イ・ロ)。
⑵ 日雇派遣の禁止
日雇派遣が禁止されていることも、派遣切りについての保護ではありませんが、派遣労働者の不安定さからの保護の一つです。
かつては、派遣労働者が1日ごとに連絡を受け、派遣先に1日単位で派遣を受けるという日雇派遣が行われていましたが、現在は30日以内の短期派遣は原則として禁止されています(労働者派遣法35条の4)。
3 派遣先企業への直接雇用
⑴ 派遣先と直接労働契約を結ぶことを強制する規定(直雇用申し込みみなし規定)
派遣社員の労働者の方の保護の制度としては、派遣先による直接雇用申し込みみなし規定があります。
違法派遣がある場合(次の①~④の場合)、派遣先が派遣労働者に直接の労働契約の申し込みをしたとみなされます(労働者派遣法40条の6第1項、2015年10月施行)。
つまり、違法派遣がある場合(①~④の場合)、派遣社員の派遣労働者の方が、「派遣先と直接雇用の労働契約を承諾します」と、労働契約締結の承諾をすれば、派遣先との間での労働契約が成立します。
⑵ 違法派遣となる場合
- 禁止業務への派遣受け入れ
港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関連業務(医師、看護師、薬剤師等)といった業務は派遣が禁止されています。 - 無許可の派遣事業者からの派遣受け入れ
2015年の労働者派遣法改正によって、すべての労働者派遣事業について、厚生労働大臣の許可が必要とされています。無許可の派遣元企業からの派遣は全て違法派遣です。 - 派遣可能期間制限をこえた派遣受け入れ
派遣元企業と有期雇用契約を締結している場合、次の二つの派遣可能期間制限があります(派遣元企業と無期雇用契約を締結している場合はこの制限はありません)。
派遣先の同一の組織単位(会社内の課やグループ単位)については継続して3年間の派遣期間の制限(労働者個人単位の派遣可能期間、労働者派遣法35条の3、40条の3)。
また、派遣先からしても、同一の事業所において受け入れられるのは、3年間が区切りで、この期間を延長する場合は、労働組合等の意見聴取等が必要とされます(事業所単位の派遣可能期間、労働者派遣方40条の2)。
これらの期間制限や意見聴取のプロセスを欠くと違法派遣になるということです。 - 偽装請負の派遣受け入れ
派遣の名を借りていますが、結局は派遣先から指揮命令を受け、賃金も事実上派遣先から支払われる等、派遣の実態がないケースです。偽装請負として、違法派遣の典型です。
4 派遣元からの期間雇用切りの保護
これについては、雇止めの禁止の法理によって契約期間満了が許されなくなる可能性があります。
⇒非正規労働者(アルバイト・パート・契約社員)の方へ
5 派遣業の労務管理で起きる労使トラブルリスク
⑴ 派遣元企業への賃金(休業手当)を請求されるリスク
派遣社員との雇用契約が残っているのに、会社の都合で仕事をさせなくなった場合、賃金を支払わないといけないことがあります。
⑵ 違法派遣がある場合は派遣先に対して労働者の地位確認の請求をされるリスク
これは、派遣先企業の問題になりますが、派遣先への直接雇用の請求については、最近の法律の改正を踏まえた判断が必要ですから、非常に難しい問題です。
専門の労働弁護士への相談は不可欠です。
⑶ 違法な雇止めによる地位確認の請求のリスク
違法な雇止めをしてしまった場合は、不当解雇のケースと同様に、派遣社員から地位確認を求められたり、契約更新による雇用継続を要求されたりすることがあります。
⑷ 派遣会社の労務管理は弁護士に
派遣の問題は法律改正も多く、適切な労務管理を行うためには、労働案件の経験のある弁護士や社労士への相談は不可欠かと思います。
お悩みの場合はすぐご相談していただくことをお勧めします。