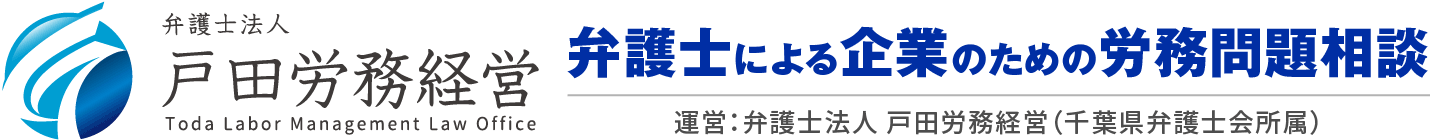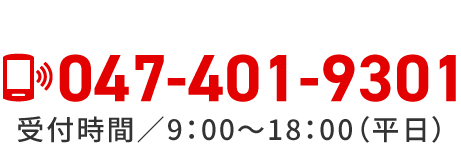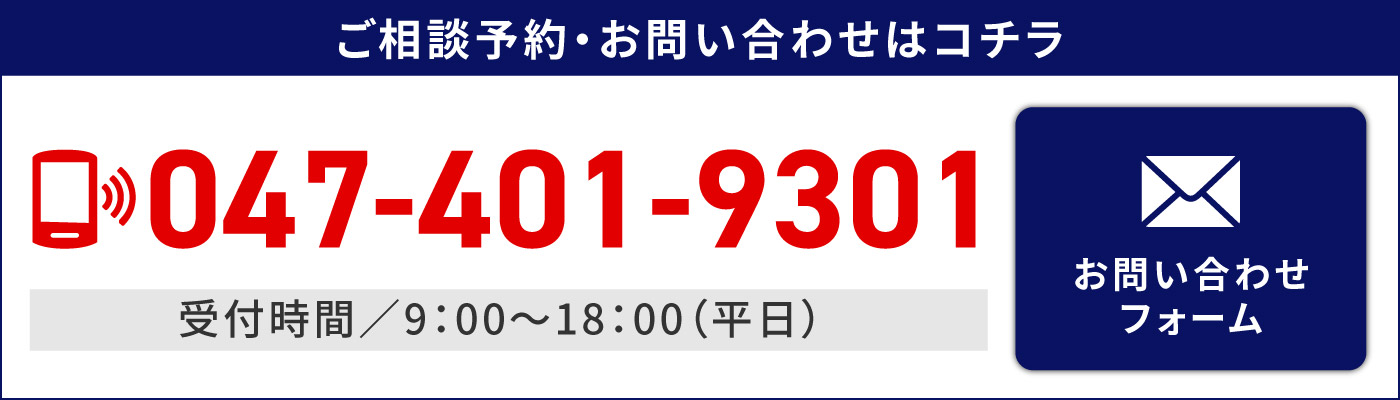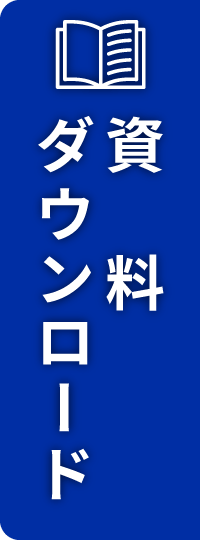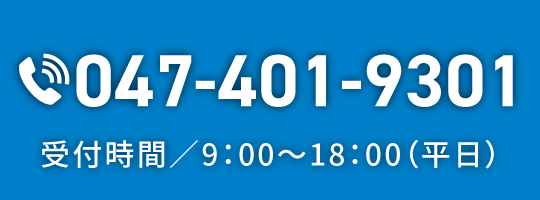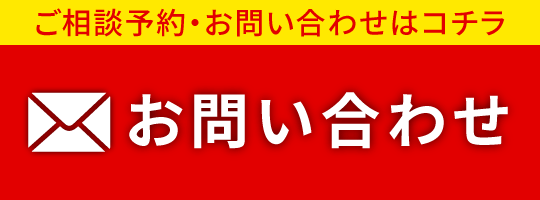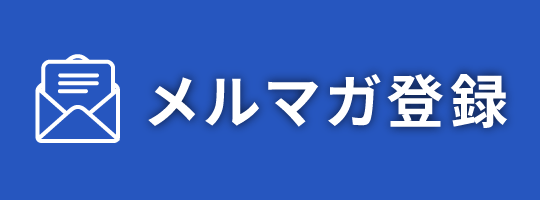緊急事態宣言に関する企業からの相談(休業手当について)
当社は都内と千葉県内で多数の学習塾を経営する企業なのですが、緊急事態宣言が発令されると学習塾も休止要請の対象になってしまいます。
さすがにこれを無視するわけにはいかないため、全教室休校としました。一部の事務職員を除いて在宅勤務も困難でして、基本的には休業するしかありません。
ただ、この宣言がいつまで続くのかもわかりません。当社の売上も激減してしまうところですが、従業員への休業手当・休業補償はどうすればよいのでしょうか。
巷では休業手当として60%を払わないといけないという話も聞きますが、うちの状態ではそれも厳しいかもしれません。法的な見解を教えてください。
【結論】
このような相談はこのところ毎日のように受けていますが、見解は分かれており、難しい問題です。緊急事態宣言発令は現時点(4月6日時点)ではまだですが、検討が必要です。
結論ですが、都道府県知事により休業を要請(休業要請)された対象業種企業については、法的には労働基準法26条の休業手当(給与60%保証)の支払は必要ないと考えます。
休業要請の対象となっていない企業の休業については、休業に至った事情によりケースバイケースですが、労働基準法26条の休業手当(給与60%保証)をするのが無難です。
(ただ、休業要請された企業についても、体力次第で、雇用調整助成金等を活用するため、一定の期間だけでも労基法26条基準の60%又はそれ以上の保障の検討をすることが雇用確保の観点からは望ましいと思います。)
休業手当の支給要件である労基法26条の「責に帰すべき事由」とは?
労働基準法26条の使用者の「責に帰すべき事由」に該当するかどうかの論点です。
労基法26条は、使用者の「責に帰すべき事由」がある休業の場合には、労働者に60%以上の休業手当を支給するべきとしています。
さて、一般には、休業手当を支給しなくてもよい場面というのは、不可抗力等の極限場面に限られると考えられています。
| 【労働基準局編労働法コンメンタール367頁】
「使用者の責に帰すべき事由」とは、第一に使用者の故意、過失又は信義則上これと同視すべきものよりも広く、第二に不可抗力によるものは含まれない |
今回の緊急事態宣言の発動があった場合、正にこの極限場面に該当するかについてです。ある程度文献にあたりましたが、なかなか正解は見当たりません。
そこで、以下は緊急事態宣言の法的根拠を踏まえて検討してみようと思います。
緊急事態宣言により事業の休止を求めることができる法律の根拠は?
緊急事態宣言により、新型インフルエンザ特措法という法律に基づく要請、つまりは「法的根拠」を持った要請や指示ができる点が重要です。
「緊急事態措置」という表現がされています。
根拠は以下の条文です。
| 第45条(感染を防止するための協力要請等)
1項 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、 2項 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、 3項 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、 第4項 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 |
特措法45条1項:外出禁止要請に基づく休業はどうか
「緊急事態宣言=休業命令」と考えている方もいるかもしれませんが、そう単純ではありません。
まず、都道府県知事は、国民に対して外出禁止の要請ができます(特措法45条1項)。
これに付随して休業をしなければならない場面がまず一つ目です。
これは、この後にお話する45条2項以下による、学校、社会福祉施設、興行場等の特定事業への直接的な休業要請とは分けて考える必要があります。
もちろん、外出自粛要請によって客が全くいない等の事情から休業に追い込まれることもあるでしょう。
ただ、この場合に労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当するかは個別の経営状況からも慎重に考える必要があります。
この場合、法的に自粛を強制される場面とまではいえないからです。自主休業とも捉えられる側面もありますので、完全に労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないとは言い切れない。
ただ、外出自粛要請自体がそれなりに強烈な効果を持ちますし、この後お話する特定事業への休業要請の影響から廻りめぐって休業を強いられることもありますので、場面によっては休業手当不要となることもあるでしょう。
このように、非常に微妙な判断となりますので、基本的には休業手当は払うのが無難です。
なお、生活に必要な病院・スーパー、コンビニ、物流その他の事業が休止されないのはこの「生活維持に必要」な場面も考慮してのことでしょう。
特措法45条2〜4項:特定の事業への休止要請(休業要請)による休業の場合はどうか
さて、問題はこちらの特定事業への休業要請です。
今回、緊急事態措置として、東京等各都道府県が検討している事業休止の要請(休業要請)は上記特措法45条2項に基づく事業施設の停止・制限要請と思われます。
東京都は、以下の三区分に分けて措置を検討しているようです。
| 【参考:令和2年4月6日時点での東京都の方針】 ① 基本的に休止を要請する施設→休業要請の対象業種 大学や専修学校など教育施設、自動車教習所、学習塾、体育館、水泳場、ボウリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、劇場、映画館、ライブハウス、集会場、展示場、博物館、美術館、図書館、百貨店、マーケット、ショッピングモール、ホームセンター、理髪店、質屋、キャバレー、ナイトクラブ、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、パチンコ店、場外車券売り場、ゲームセンター ② 施設の種別によって休業を要請する施設 ●文教施設→休業要請の対象 ●社会福祉施設→適切な感染防止の協力要請(休業要請はしない) ③ 社会生活を維持する上で必要な施設(生活インフラ)→適切な感染防止の協力要請(休業要請はしない) |
特措法の条文を見ていただくとわかるとおり、この特定事業への休業要請はそれなりに強力です。
まず施設使用制限・停止等を要請できるとされており、直接的に営業休止に関わる要請ができることになっています。行政権の行使として、その影響は甚大です。
さらに、要請を聞かない場合、都道府県の判断によって、要請よりも強い「指示」まで可能で(3項)、その場合には「公表」まで予定されます(4項)。
この公表というのが、企業名の公表までを予定しているとまでは読みきれませんが、「当該施設が」「要請に応じない」ことを前提に「指示」した旨を公表するという規定からすると、その企業名・施設名を含めた個別指示内容が公表されるようにも読めます。
小池都知事の会見でも、本来は個別の事業所・施設名を公表するのが本筋であるとの見解のようです。
| 45条の公表につきましては、基本的に施設管理者等ということになっておるので、個別の施設名だと私どもとしては解釈をしておりますけど、これについては、施設の数がかなり多くなるということもありますので、業態別にやることができないかどうかについても国といま協議をしているところです。(4月6日小池都知事の会見より引用、下線部は著者)
【引用元:東京都HP】https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2020/04/06.html |
実際の運用が待たれますが、法の建付としては無視できないでしょう。
昨今のSNSの風潮からして、この要請違反の公表によるリピュテーションリスクは甚大です。
このように、巷では「罰則がないから強制力はない」などと言われますが、単なる「お願い」とは全然違います。事実上の強制力は相当に強いと言わなければなりません。
知事から事業休止を要請された場合、企業は結局従わざるを得ない。私は労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」があると言えるかは疑問です。
緊急事態措置の休業要請による休業は、「監督官庁の勧告による操業停止」と同視できるのか
ただ、この見解に異論があることは承知しています。
ネット上のニュースではありますが、厚生労働省が休業手当支給不要との見解を述べたことで、波紋を呼んでいます。
緊急事態宣言の休業であっても休業手当を保証すべきとの主張も多数見られます。
中には、私が改訂に携わった菅野和夫教授の著書(弘文堂「労働法」12版)を引用しているものもありました。
同著では、休業手当を支給すべき例として、「流通機構の不円滑」「親会社の経営難」等と並んで、「監督官庁の勧告による操業停止」が挙げられています。
この点を指摘し、今回の緊急事態宣言での業務休止要請要請が、上記著書での「監督官庁の勧告による操業停止」に類似するため、休業手当の支給対象となるというものです。
しかし、上記著書で並列された事情(「流通機構の不円滑」「親会社の経営難」)も、かなり広いですが、いずれも会社サイドに何らか問題がある場面です。(流通の不備にも対応できる体制を作れ、親会社の経営が悪いのも使用者サイドの責任だ、という話)
ですので、「監督官庁の勧告」というのも、全て該当すると判断すべきではありません。どんな勧告なのか、どの程度の強制力があって使用者が休業せざるを得ないのかどうかなどの事情を前提にしているはずです。
緊急事態宣言によって休業要請まで出る今回の場面は、上記に説明したとおり、会社にとっては正に避けようがないどうしようもない不可抗力な事態です。
これを「使用者の責に帰すべき事由」とするのは、明らかにその文言に反した解釈です。私は賛成できません。
まとめ
以上の次第で、緊急事態宣言による事業休止要請がなされた場合においては、休業手当不支給・給与ゼロベースというのが法的には理屈が通っていると考えます。
ただもちろんこれはあくまでも法律論であって、私は全てを無給にするべきという考えではありません。
企業としても、企業の体力や、労働者の保障を最大限考え、6割ないしそれ以上の保障について、一定期限で区切りながら検討することが必要であることは言うまでもありません。
この事態だからこそ、各企業ごとの雇用確保のための努力が問われることになるでしょう。
雇用調整助成金等の制度もあります。まだまだ不透明なところも多いですが、助成金などを積極的に活用を検討して、この国難に乗り切る体制づくりをしていきましょう。