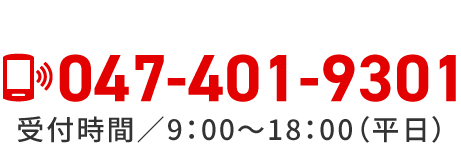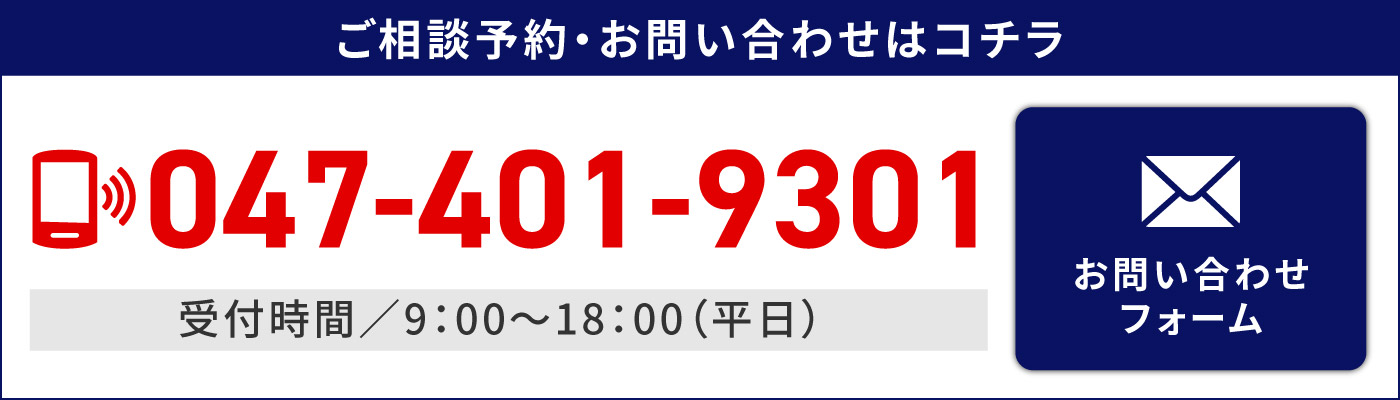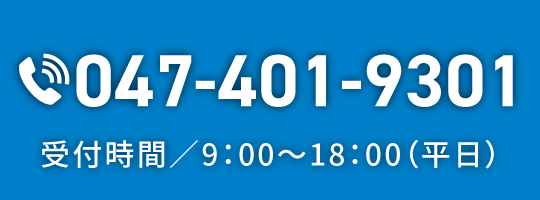はじめに
今回は、夜勤等の不活動時間についての賃金制度がどうあるべきかを考えます。
最近私が法人側を担当した事件で、夜勤の不活動時間(夜勤時間帯)の賃金の考え方について、少し面白い判断をしたものがあります。
この判決では、夜勤時間の労働時間について、その残業代計算の基礎単価について夜勤手当を基準として算定するべきとされました。これは最低賃金を下回る水準なのですが、それも違法とはならないとの判断です(千葉地裁令和5年6月9日判決)。
思い切った判断だったため、業界もややざわつきました。警備・介護等の現場に影響を与える可能性があるとして労働経済判例速報の2023年10月30日2527号のトップ判例に掲載されました。
夜勤等の不活動時間について、賃金制度がどうあるべきかの示唆に富む裁判例でしたので、詳細に紹介いたします。
なお、まだ控訴審での審理が続いておりますので、未確定な部分もあることはご承知置き下さい。
事案の概要
| 障がい者施設等を運営する社会福祉法人Yにおいて、支援員(利用者である障がい者の生活の支援を行う)として勤務するXが、利用者が日常生活を送るグループホームでの泊まり込み勤務を行った際の未払残業代を請求した事案です。 Yでは、こうした泊まり込み勤務のシフトは、前日の午後3時~午後9時のシフトから続いて翌午前6時~午前10時が基本となります。 夜勤時間帯の午後9時~午前6時までの間は、シフトとしては午前0~午前1時の1時間のみとされており、時間外割増賃金等は支給していませんでした。 なお、夜勤1回について夜勤手当6000円が支給されています。 |
争点は二つ
本件の争点については以下の2点です。
| ① 障がい者支援のグループホームでの泊まり込みの支援員の泊まり込み勤務における夜勤時間帯(午後9時~午前6時の間のうち8時間)の労働時間該当性 ② ①の労働時間該当性が認められるとした場合の、未払時間外労働に対する対価の基礎賃金の算定、割増賃金の算定の方法(夜勤手当の位置づけ等) |
夜勤などの不活動時間の労働時間が争われる事件は、0か100の結論だった
こうした事件は、ひとたび不活動時間が労働時間だとされると、不活動時間としていた全てについて通常賃金の1.25倍割増で未払賃金を算出します。
そうなりますと、夜勤1回で8時間以上もの金額が1.5割増もの金額で計算されることとなります。当然その金額は極めて大きなものとなっていました。
つまり、「労働時間該当性」という争点がクリアされてしまうと、100で負けてしまうのが常だったということです。
ところが、この地裁判決は、労働時間の該当性は認めましたが、原告の請求額のうち、20%程度のみを認めるにとどまったのです。ちょっと驚きで、この結論はやや業界的にもざわつきました。
さて、どんな内容だったのか。
労働時間該当性(争点①)はあっさり肯定される
本件の原告の夜勤勤務中は、利用者がほぼ就寝しているため、実対応はほとんどないので、労働時間に該当しないのではないかという争点です。
ここは、障がいの程度がある程度重度の者も寝泊りしていること等から、労働からの解放が保障されているとは言えないということで労働時間該当性は肯定されました。
同種の争点がされた大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)では、ビルの一室から出ることは一切許されず、呼出しがあれば即時対応することについてのマニュアル・ルールが整備されていた事案で、労働契約上の義務付けがしっかりとされていた事案でしたので、本件よりもその義務付けは強度なものでした。
同種の障がい者グループホームでの泊まり込み業務の労働時間該当性が判断された事例(グローバル事件・福岡地裁小倉支部令和3年8月24日判決=労経速2467号3頁)等もありましたが、この事案では、自殺未遂等をするような極めて重度の利用者が入所しており、対応頻度も高かったという事情もあった事案です。
当法人においては、基本的には利用者の自立的生活を促すべく、夜間にも相当のことがなければ利用者から声をかけることもないものです。実際の対応頻度も多くないことは認定されているのですが、法人にとってはやや厳しい判断になりました。
ポイントとなったのは残業代計算の基礎単価(争点②の方)
さて、ここからがポイントです。
先ほどお話したとおり、これまでの多くの裁判例では、こうした不活動時間の労働時間該当性(争点①)が肯定されると、ほぼ請求満額が認められてきていました。
ただ、おそらくこれまで会社側が、夜勤時間帯の基礎賃金等をどのように考えるのかについて正面から主張してきたケースが少ないのではないかと推察します。
賃金の基礎額の計算については次の点がポイントです。
| ① 夜勤時間帯の対価は、夜勤手当(夜勤1回で6000円とされていた)であるため、夜勤手当を基準として基礎賃金を計算(6000円÷8時間=750円)すべき。 |
| ② このような解釈は、本件では「日中勤務と比べて労働密度が薄い」点等を考慮すべきであって、労基法37条に反しないとした。 |
| ③ 賃金単価750円は最低賃金額を下回るが、最低賃金法は全ての時間帯でこれを上回ることを義務付けていないので効力は否定されない。 |
詳細な計算内容は割愛しますが、この賃金単価だと、日中賃金の半分以下になります。そして、夜勤手当分が1.0として支払われていることとなりますので、未払額は相当に少ないものとなります。
そうしたことから、判決は原告の請求額の20%程度しか認めない、という結論になったのです。0か100かという結論ではなく、その中間ともいうべき結論です。
夜勤部分の基礎単価が最低賃金を下回っても法違反はない
上記の基礎単価750円と言う数字に、「最低賃金法に違反しないのか」と思った方もいらっしゃると思います。
ただ、この裁判例は最低賃金法違反もないと判断しています。
もともと最低賃金法4条1項は、月給の場合であれば月給額から時給額を割り出した結果、最低賃金法違反になるかを検討するものです。
つまり、ある時間帯の業務の賃金が最低賃金を下回ったとしても、トータルの月給で最低賃金を上回るなら、最低賃金法には違反しないのです。
最低賃金法の規制も、すべての労働時間に時間当たりの最低賃金額以上の賃金を支払うことを義務付けるものではない。
荒木尚志「労働法(第4版)」199頁
労働密度の少ない不活動時間の賃金制度のあり方を考える
私としても、夜勤等の不活動時間について、労働時間に該当する以上は一定の義務付けがされていることや現場の負担があることは重々理解しています。
とはいえ、その労働密度というのは、日中勤務に比べて薄い仕事も沢山あります。
今回の事案でも大半の時間帯は行うべきことがないという実情がありました。他にも警備業の仮眠時間等も、実働がとても少ないケースはあります。
結局、その労働密度に応じた賃金設計と言うのは認められてしかるべきだと思っています。
労働時間が認められるかで、全て0か100の結論になってしまうことには疑問を感じます。
菅野和夫東大名誉教授も
「このような仮眠時間を完全な労働時間と同じく取り扱うことは確かに実際的妥当性に問題がある」と不活動時間についての扱い方についての問題意識を提唱しておられます(同著「労働法(第12版)」499頁)。
そして、同教授は、
所定労働時間外のある時間が労基法上の労働時間とされても、そこから当然にその時間についての賃金請求権が発生するわけではなく、賃金請求権の有無・内容は当該労働契約の解釈によって定まる
菅野和夫「労働法(第12版)」500~501頁
仮眠時間帯に特有の時間給を定めることは、最低賃金に反しない限り差し支えない
菅野和夫「新・雇用社会の法(補訂版)」203頁
として、仮眠時間等の夜勤時間帯については別途の賃金合意をすることが許容されるとしています。
この点は、安西愈先生も同趣旨の記載をしておられます。
「仮に仮眠時間が、労働からの実質的解放と認められず労働時間になる場合にも、通常の労働は行わない不活動仮眠時間の場合には、活動時間とは別の簡易業務として別の金額の賃金を定めることは、その時間の賃金が最低賃金法に違反しない限り労使の自由であるから差し支えない」
安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務(全訂7版)」418~419頁
「単に『時間外労働等につき所定の賃金を支払う旨の一般的規定を有する就業規則等が定められている場合』ではなく、当該不活動仮眠時間に『明確な』対価を定めた規定(時間外労働や深夜労働の割増賃金を含めたものでもよい)等により、当該時間の賃金が別に定められていればそれによることになる」
両先生は最低賃金法に違反しないことを前提とした賃金設計の話をしておられますが、これは先にお話したとおりで、月給の労働者についての最低賃金は月給をベースとして考えることです。
最後に
この地裁判決の結論が高裁でも維持されるかはまだわかりません。
ただ、この結論がどうなったとしても、夜勤手当等を夜間時間帯勤務の対価だと設定することは十分に可能だと思います。
「不活動時間が大半を占める時間帯の勤務については別の対価を設定できる(しかも最低賃金を下回ることもあり得る)」
ということです。
警備業・病院・福祉業界での夜勤・泊まり込み勤務については、現実と法令の狭間での苦労が絶えません。実態を踏まえた労務管理を見直していくことが必要かと思います。